芝原健太郎は「タウア・ニン最新VLSIの基礎 」を監訳・出版しました。(第1版 2002年, 第2版 2013年) 原書タイトルはFundamentals of Modern VLSI Devices です。
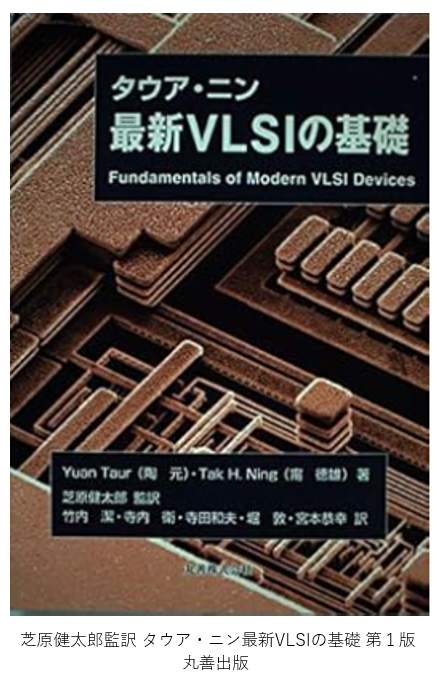
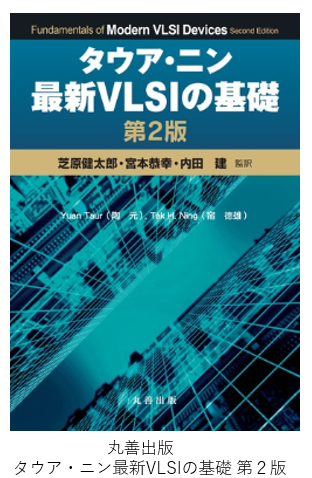
この本は教育機関・産業界の双方から非常に高く評価されており,先端 CMOS デバイス分野標準の教科書と位置づけられています。 芝原は、この本の日本語化についてVLSI Tech. Symp.2000で原著者のTaur氏と話し合いました。原著は既に日本でも良く知られていました。これを日本語化することで、大学や企業などで多くの人の役に立つに違いないとTaur氏と意見が一致しました。
数多く売れる本ではないので、少々心配しながら丸善出版さんに相談しましたが、杞憂でした。丸善出版の担当者様のもと、翻訳・監訳作業が始まりました。休日は付箋付きの原稿を積み上げて取り組みました。
竹内潔先生、寺内衛先生、寺田和夫先生、堀敦先生、宮本恭幸先生が翻訳を分担して下さいました。この本を購入しやすいように印税は合計数%に抑え、それを全員で等分しました。ですから、この先生方も、日本語版があれば多くの人の役に立つという思いで貴重な時間を割いて翻訳なさったに違いありません。
その後、原書の第2版が出て、第2版の翻訳・監訳作業が始まりました。翻訳は宮本恭幸先生と内田健先生との3人でした。場所を選ばす出来る仕事として、最後の入院生活でも続けていました。が、2011年4月には最後まで出来そうにないと思い、監訳と後の仕事を宮本先生と内田先生にお願いしました。そして両先生のお陰で無事に「タウア・ニン最新VLSIの基礎 第2版」が2013年1月に出版されました。
松波弘之 京都大学名誉教授 (追悼文集より)
2002年秋に、丸善から、『タウア・ニン 最新VLSIの基礎』(Yuan Taur and Tak H. Ning 著)芝原 健太郎 監訳 A5判・並製・610ページを出版した。5人が翻訳にかかわり、その監修であるから途轍もなくたいへんな作業であったことと想像する。
ディープサブミクロン VLSI デバイスにとって、特に重要なパラメータや性能要因に重点をおきながら、最新の CMOS (Complementary MOS)やバイポーラの基礎を解説しており、米国の有名大学の大学院1年次の教科書として使われているとのことであった。
2002年9月頃の mail から、彼の発したメッセージを記す。
>松波先生 広島大 芝原です。構想から 2 年以上の時間がかかったのですが、下記訳書を出版することができました。研究成果よりはもう少し何かしら世の中に広く役立ち、形に残る仕事がしたいと思い始めたものです。
企業在籍の方より
>>私達の世代ではSzeの教科書でデバイス物理を学びましたが、同じような内容をより現代的な視点で学ぶことができる本だと思います。最近では大学院の講義用テキストとして選ばれることも多く、後輩の東北大学出身の後輩もこれを使ったと言っていました。今からデバイスの勉強をするならSzeよりタウア・ニンだと思います。
訳を分担した東工大の宮本恭幸先生は、化合物半導体の先生で、もう20年以上もお付き合いしてきました。
この本も技術の進歩に合わせてアップデートされ、第3版ではFinFETなどの先端半導体についての内容も記載されているようです。
世界中で読まれているこんなにいい本を日本の半導体技術者が日本語で読めるようにしていただけたのは、大変有り難いことだと思います。<<
名古屋工業大学 加藤正史先生より
>>芝原先生が翻訳されたタウア・ニンの第二版も、持っていて今日見てました。直接のご面識はないのですが、芝原先生の業績は後世にも継がれていることを、お伝えください。<<
昨年、第3版が出ました。本からは芝原健太郎の名前は消えてしまいました。が、芝原の翻訳文が第3版の中のあちこちに残っているはずだという見解から、丸善出版社内では芝原健太郎を著作権を有する者のひとりとして残して頂いています。
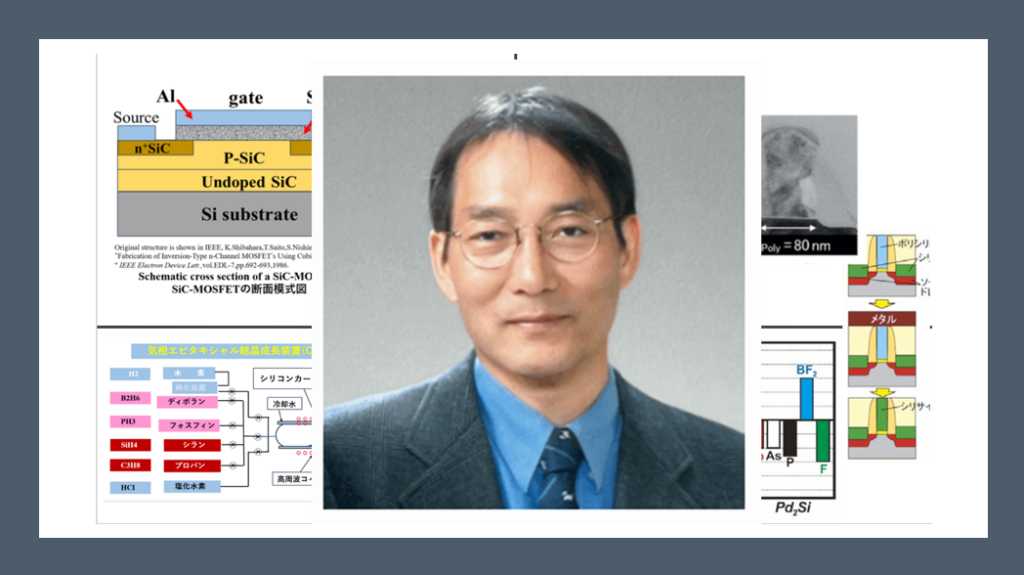
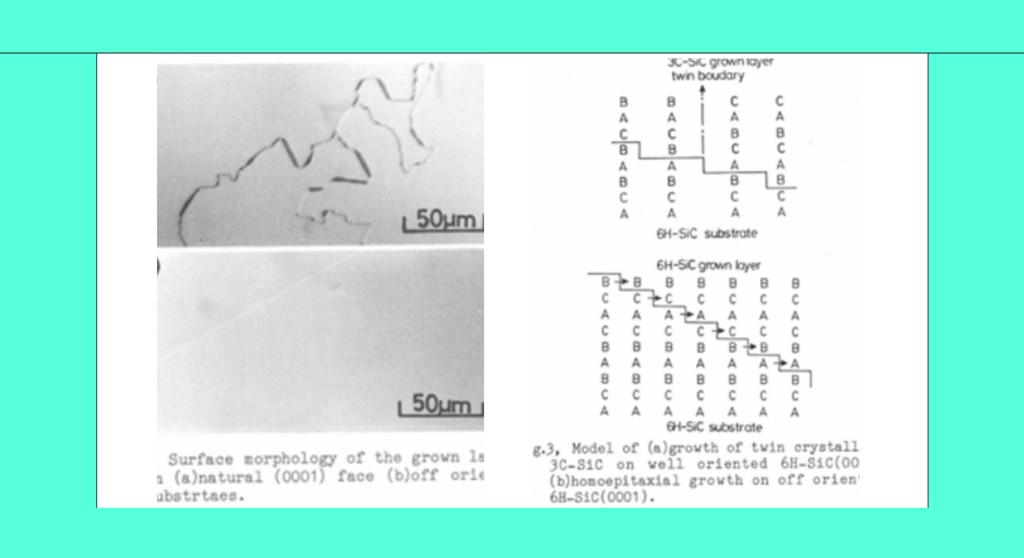

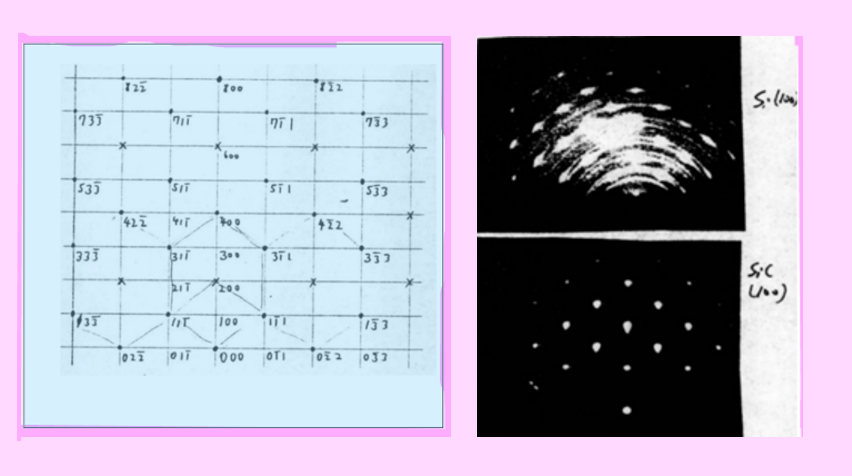
コメント